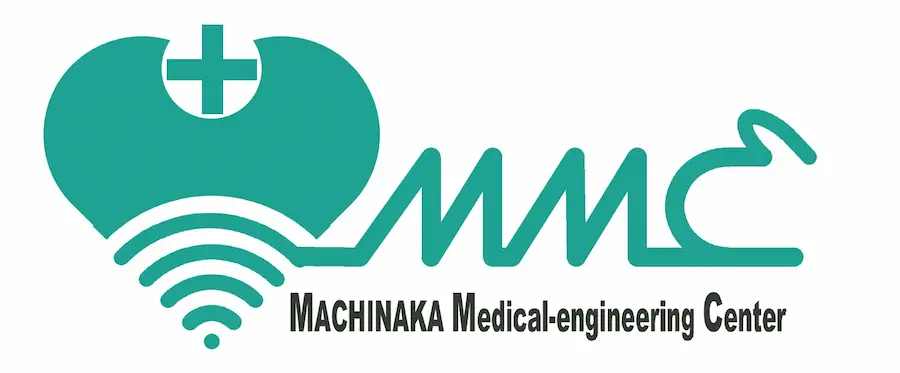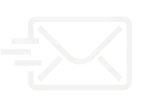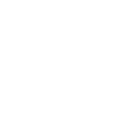弊社の動物用医療機器の開発事例

事例1 動物用パルスオキシメータ
人医療におけるパルスオキシメータの活用
パルスオキシメータの動作原理や臨床活用等の詳細の説明はこちらの記事をご覧ください。
パルスオキシメータは非侵襲的に「酸素飽和度」と「脈拍数」を測定する医療機器です。
人医療では、主に手術中のモニタリングに使用されます。モニタリングとは自動的に連続的して測定を行い、測定値の時間的な変化を監視することを言います。
手術中の患者のモニタリングに使用すると言っても、パルスオキシメータが単体で使用されることはほとんどありません。使用される医療機器は「生体情報モニタ」になります。生体情報モニタは「パルスオキシメータ」「心電計」「血圧計」等の各測定機能を内包し、一体化した複合的な医療機器です。測定項目の1つに「酸素飽和度」があるということになります。
「パルスオキシメータ」を単体で使用するケースとしては、診察時に簡易検査の目的で使用が挙げられますが、使用頻度は少ないのが現状でした。
動物医療における動物用パルスオキシメータの活用
獣医療でも、パルスオキシメータは「生体情報モニタ」の1つの機能として、手術のモニタリングで頻繁に使用されています。
また、動物病院でパルスオキシメータを、診察時に簡易検査の目的で使用する場合には、既製品では様々な問題が生じ、測定準備に手間や労力を要し、測定精度が低下することがあります。
そのため、パルスオキシメータを診察時に簡易検査の目的で使用することは稀でした。
コロナウイルス感染症の影響で状況が一変。人医療におけるパルスオキシメータの転換点
ところが、人医療ではコロナウイルス感染症が蔓延した時に、診察での簡易検査の目的で頻繁にパルスオキシメータが使用され、その有効性が実証されました。
「酸素飽和度」の検査結果が以下のような判断に使用されました。
- 持病のある人の心臓や肺の状態が、急劇に悪化することがコロナウイルス感染症の特徴となっていたため、悪化の兆候があるかどうかを簡易検査で判断
- 自宅待機中やホテル滞在中のコロナウイルス感染者を病院へ搬送すべきか、血液検査やX線検査等の精密検査を行う必要性があるかを簡易検査で判断
- 酸素投与の必要性の判断や、投与する酸素の濃度、流量の設定、人工呼吸器への切り替えの
必要性があるかを判断
感染症の早期発見は動物医療でも非常に重要であり、この影響で動物医療でも、パルスオキシメータを診察での簡易検査の目的で使用したいという声が高まりました。
動物医療において、診察でパルスオキシメータを使用しようとすると生じる問題
しかし、パルスオキシメータには、その測定原理から、体毛や色素沈着がある部位は測定不能、動いている部位は測定不能という弱点があります。
人医療では、「手術」や「診察」で使用しても指先にセンサーを装着し、体動も止めることが出来るため、弱点の影響は受けません。
獣医療でも「手術」で使用する場合は、動物は麻酔で動かず、センサーの装着部位も舌であるため、体毛や色素沈着などの弱点の影響は受けません。
ところが、獣医療で「診察」で使用する場合は、動物は覚醒しており、動き回ったり、センサーの装着を嫌がってセンサーを外したり、動物自身も体毛や色素が沈着している部位が多いため、弱点による影響を大きく受けます。
パルスオキシメータの主なセンサーの装着部位と弱点の影響
| 手術時 | 診察時 | |
| 人医療 | 「指」を覆う 体動の影響を受けない | 「指」を覆う 体動の影響を受けない |
| 動物医療 | 「舌」を挟む 麻酔により体動の影響を受けない | 「耳」を挟む 体動と体毛や色素沈着の影響を受ける |
診察で使用するパルスオキシメータの既製品は、耳にセンサーを挟んで測定する仕様となっており、具体的に、以下のような手間と問題が生じます
1.動物が測定部位を動かさないように保定が必要。
2.色素沈着がない測定部位の選定、測定部位の剃毛、外部からの光の遮光等の作業が必要。
3.1と2の影響によって、測定値の精度や再現性が悪化しやすい。
そこで弊社はこれらの問題を解決する新しい動物専用のパルスオキシメータを開発しました。開発製品の詳細を知りたい方はこちからどうぞ。
事例2動物用セントラルモニタ
人医療におけるセントラルモニタの活用
セントラルモニタの動作原理や臨床活用等の詳細の説明はこちらの記事をご覧ください。
セントラルモニタとは、入院中の患者をモニタリングする医療機器です。ICU等の集中治療室や、入院病棟等で使用されています。
セントラルモニタは、患者と直接、有線で接続する「測定器」と、ナースステーションや、担当医師と担当看護師が集まる場所に置く「表示モニタ」で構成されます。
複数の「測定器」と1台の「表示モニタ」は無線で繋がっています。測定器によってモニタリングされる測定項目が異なります。測定器は主に脈拍数等を自動的に連続して測定し、その複数人の測定データを、表示モニタに一括で表示します。
セントラルモニタを使用することで、医師や看護師は、病棟内やICU内にいる患者の容態を簡単に把握でき、患者をモニタリングするための手間や労力を削減することが可能です。
また、夜間等で医師や看護師の数が少ない時でも、患者の異変を早期に発見することで、早期対応が可能となります。
動物医療における動物用セントラルモニタのニーズ
現状の動物病院では、手動で入院動物の脈拍数・呼吸数・体温等のバイタルサインの確認を行っている施設がほとんどです。
そこで、動物病院でも、医療機器を使って入院中のペットをモニタリングしたいという声を頂いています。特に夜間の見回りによる負担を軽減したいという声が大きいです。
動物医療において、セントラルモニタの使用頻度が低い理由
ところが、セントラルモニタは主に人の病院で使用されており、動物病院での使用頻度は少ないのが現状です。
その原因は以下の通りです。
1.今のとこと、動物専用のセントラルモニタは市場にはない。従って、セントラルモニタを使用している動物病院であっても、人用を転用して入院動物に使用している。
2.人用のセントラルモニタは、測定器と表示モニタが無線接続される範囲が、病棟内に限定される。つまり、表示モニタで測定データを確認する看護師や医師が、同じ病棟内にいることが前提の仕様となっている。
動物病院では、獣医師が夜間に不在となる施設が多く、夜間は誰もいないこともある。つまり、人用のセントラルモニタを動物病院で使用しても、表示モニタで測定データを確認する人がいないため、夜間の入院患者のモニタリングは行うことが出来ない。
動物病院の現状に合わせるためには、病院の外からでも測定データを確認できる機能が必要である。
3.人用の測定器は、患者と直接、有線で接続する仕様になっている。入院中のペットはストレスフルで、体に有線でセンサーを繋いでも、嫌がってセンサーを外してしまうため、人用の測定器を長時間繋ぐことは困難である。
4.人用のセントラルモニタは動物病院にとっては非常に高価であり、既製品の人用セントラルモニタの機能を考慮すれば、購入する医療機器の優先順位が低い。
そこで弊社はこれらの問題を解決する新しい動物専用のセントラルモニタを開発しました。開発製品の詳細を知りたい方はこちからどうぞ。