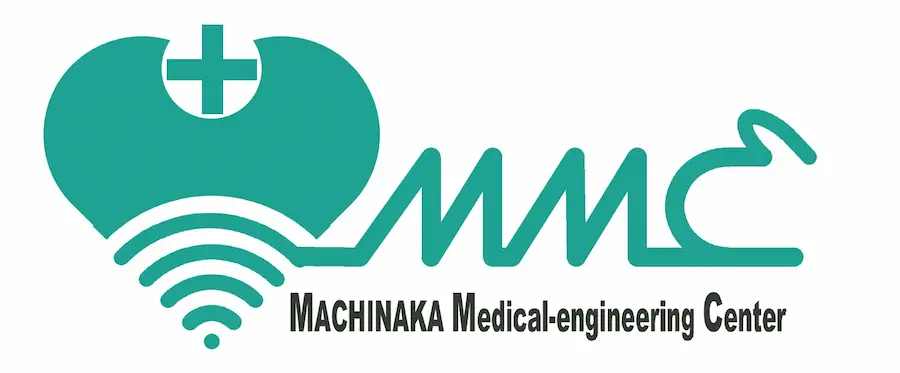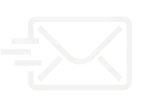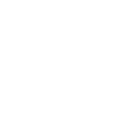パルスオキシメータとはどのような医療機器か

パルスオキシメータとは、血液中の酸素の割合を示す指標である「酸素飽和度」と、「脈拍数」を測定する医療機器です。
具体的には、血液中ヘモグロビン(酸素と結合しているヘモグロビンと酸素と結合していないヘモグロビンの合計)の内、酸素と結合しているヘモグロビンの割合を算出します。単位は%になります。
パルスオキシメータが開発されるまでは、採血を行って、血液検査で「酸素飽和度」を計測していました。
それが開発後は、皮膚の上にセンサーを取り付けるだけで、簡単に「酸素飽和度」を測定することが出来るようになりました。
現在でも、医療現場ではパルスオキシメータで測定された「酸素飽和度」をSpO2、採血して血液検査で計測された「酸素飽和度」をSaO2と表記して、区別されています。
また、パルスオキシメータが開発されたことで、それまでは血液検査で、「酸素飽和度」の値が正常か異常かを判断することが、目的だったのが、自動的に連続して「酸素飽和度」を測定出来るようになったことで、患者の容態の変化を早期に把握し、早期に対応を行うために、モニタリングの目的で使用されるようになりました。
現在では、人医療においても獣医療においても、「酸素飽和度:SpO2」は、手術の時に必ず連続測定されるモニタリング項目の1つとされています。また人医療においては、入院中の患者の容態把握のために「酸素飽和度:SpO2」をモニタリングしたり、外来で「酸素飽和度:SpO2」を検査する目的で使用しています。
パルスオキシメータの測定原理
パルスオキシメータは、酸素と結合しているヘモグロビンと、酸素と結合していないヘモグロビンでは、光線の吸光度が異なるという性質を利用して、酸素飽和度を算出します。
センサー部からは赤色光と赤外光の2種類の波長の光を測定部に照射しています。
酸素と結合したヘモグロビンは赤く見えます。これは赤色の赤色光をあまり吸収せずに反射していることを意味します。また、酸素と結合していないヘモグロビンは赤黒く見えます。これは赤色光をよく吸収していることを意味します。つまり、赤色光では、酸素と結合しているヘモグロビンと、酸素と結合していないヘモグロビンで光の吸光度に差が出ます。
一方で、赤外光では、酸素と結合しているヘモグロビンと、酸素と結合していないヘモグロビンで、吸光度に差はありません。この吸光度の違いから、酸素飽和度を算出します。
パルスオキシメータの構成
パルスオキシメータは、センサーで測定を行う測定部と、吸光度の違いから酸素飽和度を算出し、ディスプレイに測定値を表示する制御部に分けられます。以下詳細を説明します。
制御部
測定部のセンサーから収集した情報から酸素飽和度を算出する部分になります。
実は既存の人用のパルスオキシメータと動物用のパルスオキシメータで制御部分に関して大きな違いはありません。
測定部
パルスオキシメータの測定部には、センサーがあります。
センサーには赤色光と赤外光を出す発光部と、赤色光と赤外光を受け取る受光部があります。センサーには様々な分類方法があります。以下分類の例を記載します。
発光部と、受光部の配置方法による分類
センサーが透過型か反射型かによって、機器の制御方法が異なるため、透過型センサーと反射型センサーを併用して使用出来るパルスオキシメータは稀となっています。
| 透過型センサー | センサーの発光部と受光部で測定部位を挟み込むようにセンサーを配置する。一般的に最もよく使用されるセンサー。フィンガーセンサー、マルチセンサー、クリップセンサー等が該当する |
| 反射型センサー | センサーの発光部と受光部が測定部位に横並びになるように配置する。対抗機種は少ない。フラットプローブが該当する。 酸素飽和度を測定できるアップルウォッチやスマートウォッチ等に使用されているセンサー。 |
測定部位の形状によってセンサーを分類
| フィンガーセンサー(透過型) | 人の指先で測定できるセンサー 指を覆って測定する。 |
| マルチセンサー(透過型) | 人の指先等で使用する。 |
| クリップセンサー(透過型) | 人の耳等で測定ができるセンサー 耳に挟んで測定する。動物医療で最もよく使用されるセンサー。舌、耳、唇、耳介、指間等で測定する |
| フラットプローブ(反射型) | フラットな部位で使用する。使用頻度は少ない |
センサーの使用可能回数によって分類
| リユースセンサー | 繰り返しの使用することを前提としたセンサー |
| ディスポセンサー | 基本的には1回の使用で廃棄することを前提としたセンサー。透過型のセンサーが多い。 |
センサーはどのように選択するべきか
測定部位やどのような場面で使用するかによって適切なセンサーを選択することが重要です。測定部位によって適切な形状のセンサーを選択する必要があります。動物でよく使用されるセンサーはクリップ型で、測定部位には、舌、耳、唇、耳介、指間等が挙げられます。参考までに、各センサーの特徴をご紹介します。
リユースセンサーの特徴
| センサーの形状 | フィンガーセンサー(透過型) | マルチセンサー(透過型) | クリップセンサー(透過型) | フラットプローブ(反射型) | |
| 長所 | 人医療で最も使用されるセンサー | サイズの微調整が可能。 | 獣医療で最も使用されるセンサー。 | 測定部位を挟む必要がない | |
| 短所 | 手指での使用に特化 | 隙間が生じやすい。光干渉しやすい。動物では剃毛が必要 | 測定部位圧迫が生じる。光干渉しやすい。動物では剃毛が必要 | 凹凸がなく、密着する部位で使用。動物では剃毛が必要 | |
| 測定部位 | 人 | 手指を覆う | 足指、手指に巻く | 耳に挟む | 額に張り付ける |
| 動物 | 使用は推奨されていません | 足裏などで使用可能 | 舌、耳、唇、耳介、指間に挟む | 尾根部に巻く。直腸に挿入する | |
ディスポセンサーの特徴
| 長所 | 新生児用・幼児用・小児用・成人用など様々なサイズのセンサーが選択できる。 動物病院では様々な動物がいるので、サイズに合ったセンサーを選択しやすい | |
| 短所 | 1回のみ使用が前提となっている。テープで固定するため取り外しにくい。高価である。動物では部位次第で剃毛が必要 | |
| 測定部位 | 人 | 新生児・幼児・小児・成人の手指・足指に巻き付ける |
| 動物 | 小動物・中動物・大動物の尾根に指間に巻き付ける | |
弊社では、直腸で測定が出来る動物用パルスオキシメータを開発しました。直腸内は体毛や光干渉による影響を受けません。また直腸には密着性があり、小型や大型の動物に合わせてセンサーサイズを変える必要もなく、上記のような使用間違いが起因したトラブルは生じにくい仕様になっています。
弊社のパルスオキシメータは、診察で使用することに特化しており、診察時の検温作業で、直腸温と同時に酸素飽和度と脈拍数を検査できます。
ご興味を持って頂けましたら、こちらから製品の詳細をご覧下さい。