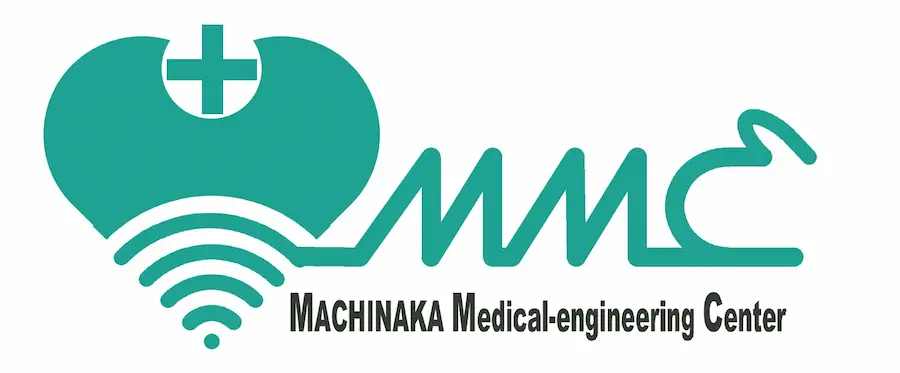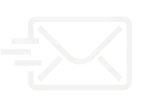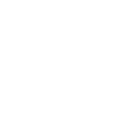臨床現場で実際に起こったパルスオキシメータのトラブル事例をご紹介

獣医師の皆さん。動物看護師の皆さんこんにちは
こちらの記事で病院内で発生した医療機器全体のトラブルの種類を紹介させて頂きましたがご覧になって頂けたでしょうか?
簡単にまとめると、病院の中で発生する医療機器のトラブルの内、全体の約6割がメンテナンスの不実施に起因したトラブル、約3割が使用者の使用間違いが起因したトラブル、約1割が機器本体のトラブルでした。
今回は、医療機器の中でも特にパルスオキシメータに絞って、私が経験した使用間違いによって、動物病院で実際に起こったトラブルの事例1例と、人医療の現場で実際に起こり、動物病院でも起こり得るトラブルの事例2例をご紹介いたします。
トラブル事例1
トラブルの内容
人医療の産婦人科病棟で看護師さんが女性に対して、パルスオキシメータで酸素飽和度:SpO2を測定したら、測定値がおかしいという連絡がありました。患者さんは元気に話していて、とても異常があるように見えないが測定値は異常で、機器の故障が疑われるということでした。
原因と対応
患者さんの測定部位の指先を確認したところ、爪にマニキュアが塗っていることが確認できました。マニキュアを塗った爪にセンサーを付けると、塗料の色素によって光の吸光度が大きく変動します。そのために「酸素飽和度:SpO2」測定値が低い値となっていました。爪にマニキュアが塗っていない他の指に測定部位を変更したところ、正確に測定が出来ました。パルスオキシメータでの測定は色素沈着のある測定部位を避ける必要があります。
動物病院でも起こり得る同様のトラブル
獣医療では、既存のパルスオキシメータの測定部位として選択されやすいのは、舌、耳、唇、耳介、指間等が挙げられますが、例えば、動物によっては、舌に色素があり一部が黒かったり、耳の一部がシミみたいに黒くなっていたり、指間や肉球の一部の皮膚が固くなり変色している場合もあります。パルスオキシメータを動物に使用する際には、このような色素沈着部位は避ける必要があります
また、人の場合、測定部位である指先に体毛があることは少ないですが、動物は全身が毛に覆われています。動物の体毛は光を反射する性質があり、色素沈着の場合と同様に光の吸光度が変動するため、体毛をそのままの状態で測定すると、測定値が大きく変動します。
体毛部は剃毛を行い測定するか、測定部位を変更することが必要です。
体毛の程度によっては、剃毛しなくてもディスプレイに測定値が表示され、測定が出来ると判断する方もいらっしゃいますが、測定精度を担保するためには剃毛作業が必要です。また、透過型のセンサーの場合は、発光部側と受光部側の両面の剃毛が必要になります。
トラブル事例2
トラブルの内容
動物病院から小型犬の手術で使用していたパルスオキシメータの酸素飽和度:SpO2の測定値が非常に不安定で、値がよく変動する。買ったばかりなのに機器が故障しているのではないか。何が原因か分からないので動作確認を行ってほしいという連絡を受けました。
手術後にパルスオキシメータの動作確認を行いました。
動物病院で生じたトラブルの原因と対応
パルスオキシメータの動作確認を行っても、測定値は安定していて測定精度の異常は確認できませんでした。そこで、使用中の状況をヒアリングしました。手術中に発生したことから、以下の2つの原因が疑われました。
①測定部位が舌で、術野と近かったことから、無影灯の光がセンサーの受光部に当たったことが原因で、センサーの受光部が外部からの光で干渉を受けたのではないか。②測定部位は舌で、長時間のモニタリングで使用していたことから、唾液等の影響でセンサーが滑りやすくなるため、測定部位とセンサーの密着が弱くなり隙間が生じたことで、測定値が不安定になったのではないかと推測しました。
クリップセンサーを舌で使用する場合には、センサーの受光部と、測定部位の間に薄いガーゼを濡らして挟むことで、センサーの受光部の遮光と、センサーの密着性の確保が出来るので、試してもらうようにお願いし、それでも同じ現象が発生するようであれば、再度連絡して頂くようにお願いしました。結果的にその後はトラブルが発生しませんでした。
人医療で最もよく使用されるフィンガープローブセンサーは測定部位をセンサーで覆うため、光干渉の影響は受けにくいですが、獣医療でよく使用されるクリップ型のセンサーは測定部位を挟んで使用するため、受光部が露出し光干渉を受けやすくなります。更に測定部位によってはセンサーを固定しにくい場合もあり、センサーの一部が浮いていないか、密着しているか等の確認が必要です。
トラブル事例3
トラブルの内容
人医療の産婦人科外来で、看護師から男児にパルスオキシメータで酸素飽和度:SpO2を測定したら、全く測定できない。ディスプレイに測定値が表示されずアラームが鳴るという連絡を受けました。
原因と対応
単回使用のディスポセンサーが使用されていましたが、センサーの発光部から赤色光が確認出来たことから、機器本体やセンサーには異常がないと判断しました。機器やセンサーが故障している場合は、センサーの発光部から赤色光は確認出来ません。
使用しているセンサーは小児用のセンサーでしたが、測定している患者は幼児でした。センサーのサイズと、測定部位のサイズが合っておらず、センサーのサイズが大きいため、発光部、測定部位、受光部が、一直線上に固定されていないことが、測定が出来ない原因でした。
適切なサイズのセンサーを用意し使用したところ、測定が出来ました。患者さんのサイズに合った適切なサイズのセンサーを使用するように依頼しました。
動物病院でも起こり得る同様のトラブル
動物病院でも小型~大型まで様々なサイズの動物に対して、パルスオキシメータを使用することがあります。動物のサイズに合った適切なサイズのセンサーを使用しないと、測定精度の低下や測定自体が出来ないといったトラブルが生じます。
また、パルスオキシメータのセンサーには様々な形状があり、測定部位によって適切な形状のセンサーを選択する必要があります。動物でよく使用されるセンサーはクリップ型で、測定部位には、舌、耳、唇、耳介、指間等が挙げられます。参考までに、人用と動物用を含めて、市販のパルスオキシメータではどのようなセンサーがあるのかをご紹介します。
リユースセンサーの特徴
| センサーの形状 | フィンガーセンサー(透過型) | マルチセンサー(透過型) | クリップセンサー(透過型) | フラットプローブ(反射型) | |
| 長所 | 人医療で最も使用されるセンサー | サイズの微調整が可能。 | 獣医療で最も使用されるセンサー。 | 測定部位を挟む必要がない | |
| 短所 | 手指での使用に特化 | 隙間が生じやすい。光干渉しやすい。動物では剃毛が必要 | 測定部位圧迫が生じる。光干渉しやすい。動物では剃毛が必要 | 凹凸がなく、密着する部位で使用。動物では剃毛が必要 | |
| 測定部位 | 人 | 手指を覆う | 足指、手指に巻く | 耳に挟む | 額に張り付ける |
| 動物 | 使用は推奨されていません | 足裏などで使用可能 | 舌、耳、唇、耳介、指間に挟む | 尾根部に巻く。直腸に挿入する | |
ディスポセンサーの特徴
| 長所 | 新生児用・幼児用・小児用・成人用など様々なサイズのセンサーが選択できる。 動物病院では様々な動物がいるので、サイズに合ったセンサーを選択しやすい | |
| 短所 | 1回のみ使用が前提となっている。テープで固定するため取り外しにくい。高価である。動物では部位次第で剃毛が必要 | |
| 測定部位 | 人 | 新生児・幼児・小児・成人の手指・足指に巻き付ける |
| 動物 | 小動物・中動物・大動物の尾根に指間に巻き付ける | |
弊社では、直腸で測定が出来る動物用パルスオキシメータを開発しました。直腸内は体毛や光干渉による影響を受けません。また直腸には密着性があり、小型や大型の動物に合わせてセンサーサイズを変える必要もありません。
弊社のパルスオキシメータは、診察で使用することに特化しており、診察時の検温作業で、直腸温と同時に酸素飽和度と脈拍数を検査できます。
ご興味を持って頂けましたら、こちらから製品の詳細をご覧下さい。